
今回は審判との関係性についてのお話です。
全国軟式野球連盟や地域のリーグに所属している方には是非読んでもらいたい内容です。
野球の試合において、審判の存在は無くてはならない存在です。
たった1つの判定が試合を左右することは少なくないはず。
相手に有利な判定が原因で試合に負けたと思うこともしばしば経験したことがあるのではないでしょうか?

自分たちに不利な判定をされた時の方が記憶に残り易いので、負けた時の印象の方が残り易いですね。
だからと言って審判に対して暴言を吐くとか、審判に聞こえるように判定に対してケチをつけるのは私は好きではありません。
私達が試合を楽しめるのは審判員がいるからこそなのです。
普段から感謝の気持ちを持つことが大切だと考えています。
審判に感謝の気持ちを持った方が良い理由
野球の審判に関わらず自分と関わる人に対して感謝の気持ちを持つことは大切です。
その1つが野球の審判員というだけのこと。
私達が感謝の気持ちを持って審判員と接することで、相手にもその気持ちが必ず伝わります。
そしてお互いに信頼関係が生まれます。
信頼している審判員に試合の判定を任せることができれば、安心してプレーに集中できることでしょう。
信頼関係を築く方法

では、
どのように審判員に接すれば良いのでしょうか?
それはいたって簡単で当たり前の事を継続するだけで良いのです。
審判員って正しい判定をして当たり前、誤審すると非難を浴びる辛い役割です。
際どいタイミングや際どいコースでも正しく判定された事を試合後にそれとなく伝えてあげるのも良いかも知れません。

称賛される事は殆ど無いでしょうから嬉しいはずです。
また絶対にやってはいけないこともあります。
そこをグッと我慢しましょう。
せめて審判に聞こえないような小声でチームメイトに話しかけるくらいに留めておきましょう。

人間誰しも自分が下した判断を否定されることは嫌なものです。
審判と信頼関係を築くメリット・デメリット
では審判員と信頼関係を築く事ができれば、どのようなメリットがあるのか解説していきましょう。
自チームに有利に判定されるようになる。
って甘い事は殆どないと思って良いと思います。
私が最もメリットを感じることは、試合を安心して預けることが出来る。ということです。
審判の判定が信頼できるからこそ自分のプレーに集中できるとは思いませんか?
審判員が信頼できないと際どい判定に対していちいち疑問が生じたり、自分に不利な判定の場合は腹が立ったりすることかと思います。そうなればプレー以外に意識が分散してしまい、結果的に集中力を欠いてしまうことに繋がるでしょう。
ちょっとした事かもしれませんが、注意が散漫になればミスを誘発し易くなり、そのワンプレーで試合の流れが変わってしまったり、時には試合の行方を左右することになりかねません。
(野球とはそれ程些細な事で勝敗が決まる事が多々あるスポーツだと思っています)
では、逆にデメリットをご紹介。
と言いたいところですが、現時点の私の経験上で審判員と信頼関係を築くことによるデメリットが思い当たりませんでした。

もしどなたか「こんなデメリットがあるよ!」という方がいましたら、コメント欄にご意見をお寄せ下さい。
もし納得いかない判定をされたらどうする?

でも、どうしても納得のいかない判定をされた場合はどうすればよいのでしょうか?
草野球ではリクエスト制度(ビデオ判定)が無い為、一度判定した結果が覆ることは滅多にありません。
その場で審判の判定にケチをつけると、悪い印象を与えることはあっても今後のことを考えると良い結果に結びつくことがありません。
従って、
事後にその判定をした審判員になぜそのように判定をしたか理由を聞くようにしています。
例えばストライク or ボールの判定の場合を考えてみましょう。
自分がバッターの場合だと、判定の直後に「今のコースはギリギリ入っていたんですか?」と主審に聞きます。
そうすることで、そのコースがギリギリのラインかどうか線引きすることができます。
勿論審判員も次にそのコースにボールが来た場合は意識するはずですので、ストライク/ボールの判定がブレる事は少なくなります。
また、自分の感覚とのギャップを知ることができるでしょう。
逆に自分が捕手の場合も同様です。
どこがその日の審判のストライク/ボールの境界線なのか明確になる為、配球を組み立て易くなるでしょう。
まとめ
審判員と信頼関係を築くことができれば、我々は細かい判定を気にせず自分自身のプレーに集中することができます。
では審判員と信頼関係を築く第一歩として以下のことを実践してみましょう。
・試合後に”ありがとうございました”とお礼を言おう
・その日の試合内容について会話しよう
最後に、
自分達が試合できるのも審判の方々の協力があってこそです。
審判員には常日頃から敬意の気持ちを持って接することが大切です。
最後まで当ブログを読んで頂きありがとうございました。
以上




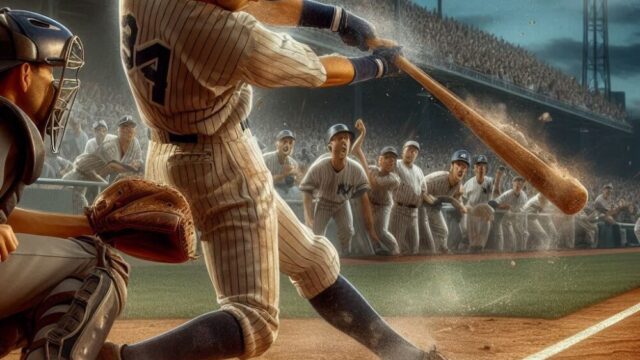
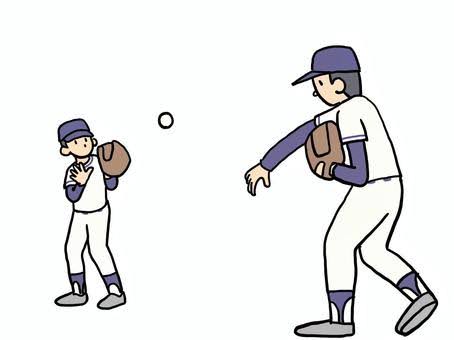










コメント